Googleが開発したAIノートブック「NotebookLM」は、アップロードした資料をもとに要約や質問応答を行える革新的な生成AIツールです。
従来のAIと異なり、自分の手元の情報だけを使うため精度が高く、研究・教育・ビジネスなど幅広い場面で活用されています。
本記事ではNotebookLMの特徴や主要機能、料金プラン、ChatGPTやGeminiとの違い、活用事例や注意点までを徹底解説します。
本内容はYouTube動画でも解説しております。
Google発のAIノートブック「NotebookLM」とは?

NotebookLMは、Googleが開発したAI搭載ノートブック型の情報整理ツールです。最大の特徴は、インターネット上の情報を直接参照するのではなく、ユーザーがアップロードした資料のみを情報源として活用できる点にあります。
そのため、従来の生成AIで問題視されていた「誤情報(ハルシネーション)」のリスクを大幅に抑え、信頼性の高い回答を得ることが可能です。
サービスはもともと2023年に「Project Tailwind」として試験的に提供され、2025年現在では Google One AI Premiumプラン や Google Workspace の一部機能として利用できるまでに進化しました。個人ユーザーから企業利用まで幅広い層を対象としており、研究やビジネス文書の整理、学習支援など多様な用途に対応しています。
また、日本語への対応も進み、文章要約や質問応答に加えて、資料内容を音声でまとめる「音声概要」機能、さらにはスマートフォンから利用できるアプリも登場しました。
スマホアプリの登場により、移動中やスキマ時間でも効率的にインプットが可能となり、従来のノート管理ツールを超えた「AIリサーチパートナー」として注目を集めています。

NotebookLMの特徴

NotebookLMには、従来の生成AIや一般的なノート管理アプリと比べて大きく異なる特徴があります。
特に「ユーザー資料に基づいたAI応答」の仕組みにより、正確性と信頼性を兼ね備えたツールとして高く評価されています。
ここでは代表的な4つの特徴を解説するので、NotebookLMへの知見を深めましょう。
アップロード資料ベースのAI応答で安心
NotebookLMは、ユーザーがアップロードした資料(Googleドキュメント、PDF、スライド、Webサイト、YouTube字幕など)を情報源としてAIが回答を生成します。
つまり、インターネット上の不確かな情報を勝手に参照することはなく、あくまでも自分の持っている資料だけに基づいて答えてくれるのです。
そのため、社内規程や契約書、研究資料などの扱いに適しており、ビジネスや学習において安心して活用できます。
ハルシネーションが起きにくい高精度回答
一般的な生成AIは、もっともらしいが根拠のない情報を生成してしまう「ハルシネーション」が課題です。
しかし、NotebookLMは参照する情報源が明確に限定されているため、誤情報を混ぜるリスクを大幅に低減できます。
特に企業の業務や学術研究のように「正確性が重視される領域」において大きな強みといえるでしょう。
根拠リンク付きで信頼性を担保できる
NotebookLMの回答には、常に参照した資料の出典リンクが付与されます。
一つの情報に対して一つ以上の番号が横に表示され、番号をクリックすれば自身が提供した複数ある資料の中からどの資料を参考にしているのかが判断可能です。
そのため、回答がどの情報に基づいて生成されたのかをユーザー自身で確認できるため、業務上の意思決定や学習における信頼性を担保できます。
Googleドキュメント・スライドなどGoogleサービスとの連携が便利
Googleが提供するサービスであるため、Googleドキュメントやスライド、Googleドライブとの親和性が非常に高い点も魅力です。
Googleドキュメントやスライドで受け取った資料を要約したいときや、マニュアルから一部の内容を抜き出したいときなど、資料をアップロードすれば簡単にできます。
日常的にGoogle Workspaceを利用している企業や教育機関にとっては、既存のワークフローにスムーズに組み込むことが可能です。
資料のアップロードや共有、共同作業がより効率的に行えることから、ワークフローの理解が早まり、質問もNotebookLMで解決できます。

NotebookLMの主要機能

NotebookLMには、単なるノート整理を超えた多彩な機能が搭載されています。
資料を効率的に読み解き、要約・質問応答・知識の再利用をサポートする仕組みが整っているため、業務や学習の効率を大幅に向上可能です。
ここでは代表的な機能を紹介します。
高度な要約・質問応答
NotebookLMはアップロードした資料をAIが解析し、要点を抽出して短時間で要約を生成可能です。
長文のレポートや論文でも、主要な論点を一目で把握できるため、調査や事前準備に役立ちます。
また、資料に基づいて質問をすれば関連部分を参照しながら回答してくれるため、文書を隅々まで読む手間を大幅に省けます。
音声解説(ポッドキャスト風の音声サマリー)
2025年のアップデートで強化された「音声解説」機能では、資料内容をポッドキャストのような会話形式の音声で出力できます。
男性と女性の対話形式で出力され、いかにもポッドキャストで配信しているかのような形になり、楽しみながらアップロードした資料の内容を把握可能です。
日本語を含む複数言語に対応しており、国際的な情報収集にも役立ちます。移動中や作業中でも耳から学習できるため、スキマ時間の活用に最適です。
多様な形式に対応したアップロード方法(PDF、動画、音声、URLなど)
NotebookLMでは、Googleドキュメントやスライドに加え、PDF・テキストファイル・YouTube動画・音声ファイルなど、幅広い資料形式をソースとして読み込めます。
異なるフォーマットの情報を一つのノートブックにまとめて整理・分析できる点は、他のノートアプリにはない強みです。
たとえば、一つの情報をリサーチする際に複数のサイトやYouTube動画を参照する場合が挙げられます。NotebookLMを使用すれば10以上の資料から情報を抜き出して知りたい内容を教えてくれるので、素早く知りたい内容のみを把握可能です。
ノート保存・編集・共有機能
生成された回答や要約は、そのままノートとして保存でき、必要に応じて編集・追記することも可能です。
さらに、作成したノートは社内メンバーやチームと共有できるため、ナレッジマネジメントや共同作業に役立ちます。
ただし、質問や指示に対して表示されたチャットの内容は保存されません。残しておきたい内容は、すべてレポートとして出力しなければならないので、注意しましょう。
Google Workspaceを利用していれば、アクセス権限を細かく設定しながら安全に共有できます。
Studioパネル(メモ・FAQ生成など)
NotebookLMの右側に表示される「Studio」パネルには、AIとの対話をさらに発展させる機能が搭載されています。
重要な回答を保存できる「メモ機能」や、読み込んだ資料からAIが自動的に想定問答集(FAQ)を生成してくれる機能があります。
Studioパネルを活用すれば、会議の議事録作成や社内FAQの作成を効率化でき、情報整理の幅が大きく広がります。

NotebookLMの料金プランとは?

NotebookLMは無料で気軽に使える一方、利用上限が拡張された有料プランが用意されています。
| 項目 | 無料プラン | 有料プラン(NotebookLM in Pro) |
|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 月額2,900円~(Google One AI Premium) |
| 主な対象者 | 個人利用、ブロガーや情報収集向け | 業務利用、フリーランスや中小企業向け |
| ストレージ容量 | 15GB | 2TB |
| ノートブック作成数 | 100個まで | 500個まで |
| 1ノートブックあたりのソース数 | 50個まで | 500個まで |
| チャット回数/日 | 50回まで | 300回まで |
| 音声生成回数/日 | 3回まで | 20回まで |
| 独自機能 | 基本機能のみ | ・音声による要約生成・回答スタイルの調整・チーム共有と利用状況分析・優先処理による高速応答 |
利用目的や業務規模に合わせて適切なプランを選ぶことで、効率的に活用可能です。
無料プラン
NotebookLMは、Googleアカウントさえあれば誰でも無料で利用を開始できます。
基本的なノートブック作成や資料アップロード、質問応答・要約といった主要機能はすべて体験可能です。
ただし、アップロードできるソース数や1日あたりの質問回数には制限があり、業務で集中的に使いたい場合には物足りなさを感じるかもしれません。
有料プラン(NotebookLM in Pro(旧Plus))
より本格的にNotebookLMを使いたい場合は、有料プランの利用がおすすめです。
有料プランは、NotebookLMを契約するのではなく、下記のGoogleサービスに付随しています。
- Google One AI Premium
- Google WorkspaceのBusiness Standard以上のプラン
- Geminiアドオン契約
有料プランにアップグレードすると、ノートブックの作成数や登録できる資料(ソース)の数が無料プランの5倍以上に増加します。さらに、音声解説の生成数が1日20回まで引き上げられるので、より多くの情報を音声生成可能です。
ほかにも、回答スタイルをカスタマイズでき、文体や長さを目的に応じて自由に調整できます。
また、複数人で使用する場合にも、有料プランの契約がおすすめです。作成したノートブックを社内で共有し、誰がどの情報を活用しているかを分析する機能が利用できます。
たとえば、AIの活用が得意な社員と不得意な社員を把握でき、個人の能力に合わせて指導可能です。
企業向けEnterpriseプラン
大規模にNotebookLMを導入する企業向けには、Enterpriseプランが提供されています。
大量のノートブック管理やチーム単位での共有・権限設定、セキュリティポリシーの適用など、業務利用に必要なセキュリティに特化した高度な管理機能が揃っています。
バックオフィスや研究開発部門での大規模データ活用、社内ナレッジ基盤としての利用に適しています。
ChatGPTやGeminiとの違い

NotebookLMは「自分のアップロードした資料だけを参照する」という点で、ChatGPTやGeminiと大きく異なります。
ここでは、情報源・用途・信頼性などの観点から違いを解説するので、それぞれの内容を把握してNotebookLMを使いこなしましょう。
情報源の違い(ユーザー資料限定 vs 広範な知識)
NotebookLMは、ユーザーがアップロードしたPDF、Googleドキュメント、スライド、動画、音声ファイルなどを情報源として回答を生成します。
提供していない外部のインターネット情報を直接参照することはありません。
一方、ChatGPTやGeminiは事前学習済みの膨大な知識や、Web検索から得られる情報をベースに回答を生成します。
用途の違い(正確な要約/整理 vs アイデア創出・文章生成)
NotebookLMは、与えられた資料の内容を正確に整理・要約し、ユーザーの質問に応答することを得意としています。
複数の文書を横断的に分析したり、文献を比較したりする用途に最適です。
一方、ChatGPTやGeminiは、幅広い一般知識を活用してアイデアを生み出したり、文章をゼロから作成したりする場面に強みがあります。
たとえばマーケティングコピーの生成や新しい企画のブレストなど、創造性を必要とするケースに活用可能です。
信頼性の違い(出典リンクあり vs ハルシネーションリスク)
NotebookLMの回答には必ず参照元のリンク(資料内の該当箇所)が表示されます。
そのため「この答えの根拠はどこか?」をすぐに確認でき、信頼性が担保されやすい仕組みといえるでしょう。
一方、ChatGPTやGeminiは一般知識をもとに文章を生成するため、もっともらしいが誤った情報(ハルシネーション)が含まれるリスクがあります。
特に専門的な分野や最新情報では、ファクトチェックが欠かせません。
使い分けのポイント
- NotebookLM:社内マニュアル、契約書、論文、研修資料など「手元の資料を正確に整理・要約したいとき」に最適。
- ChatGPT/Gemini:新しいアイデアを出したいとき、一般的な知識を活用したいとき、ゼロから文章やコードを生成したいときに適している。
両者を上手く組み合わせることで、「正確な情報整理」と「柔軟な発想」の両方を手にすることができます。

NotebookLMの使い方・始め方ステップ

NotebookLMは、Googleアカウントさえあれば誰でも使い始めることができます。
ここでは、初めて利用する方向けに基本のステップを解説します。
ステップ1:公式サイトにアクセスしGoogleアカウントでログイン
まずは NotebookLM公式サイト にアクセスします。
個人のGmailアカウントや企業のGoogle Workspaceアカウントでログインすれば、すぐに利用可能です。
ステップ2:ノートブックを作成し資料をアップロード
ログイン後、「新しいノートブック」を作成してください。
ここでまとめたい資料(ソース)をアップロードします。
対応している形式は以下の通りです。
- PDFファイル
- Googleドキュメントやスライド
- YouTube動画(字幕データを読み込み)
- 音声ファイル(自動文字起こし対応)
- テキストファイルやWebサイトURL
複数の形式をまとめてアップロードできるので、関連する資料を一括で読み込ませると効率的です。
ステップ3:チャットで質問・要約を生成
資料が読み込まれると、中央のチャットパネルでAIと対話できるようになります。
「この資料の要点を3つにまとめて」
「第2章の結論は何ですか?」
「3社の契約条件を比較してください」
など、自然な言葉で質問すれば、AIが該当箇所を引用しながら回答してくれます。
回答には根拠リンクが付いており、クリックすればすぐに元の資料にアクセス可能です。
ステップ4:ノートやメモに保存・共有
気になる回答は「ノート」として保存し、後から編集や追記ができます。
右側の「Studioパネル」を活用すれば、重要ポイントのメモやFAQ形式の自動生成も可能です。
さらに、ノートブックを共有してチーム全体で活用することもできます。
Proプランでは「チャットのみ共有」といった詳細なアクセス制御も設定可能です。
NotebookLMの活用事例

NotebookLMは、資料ベースで正確な要約・質問応答ができる点を活かして、幅広い業務シーンで導入が進んでいます。
ここでは代表的なケースを部門別に紹介します。
バックオフィス業務
人事・総務・経理などのバックオフィス部門では、社内規程や契約関連の確認作業に大きな効果を発揮します。
- 就業規則や福利厚生に関する社員からの質問に、AIが24時間自動応答
- 経費精算や出張規程のルール確認を効率化
- 複数の契約書から共通条項や差分を抽出し、比較表を瞬時に作成
属人化しがちなバックオフィス業務を効率化し、担当者の負担を軽減できます。
営業・マーケティング
営業現場では、提案の精度や顧客対応のスピードアップに役立ちます。
- 過去の提案資料やヒアリングメモをまとめて読み込み、提案の骨子を自動生成
- 商談の録音を文字起こしして要点を抽出し、顧客の関心ポイントを整理
- マーケティング部門では、市場調査レポートを横断的に分析し、ターゲット層ごとのインサイトを抽出
資料探しにかかる時間を削減し、営業力・マーケティング力の強化につながります。
人事・教育
新入社員教育や社内研修でもNotebookLMは効果的です。
- 規程や業務マニュアルを読み込ませ、新人が自分で質問して学習できる環境を構築
- 過去の研修資料やアンケートを分析し、改善点を自動で抽出
- FAQ自動生成機能を使って「社員が疑問に思いやすい質問集」を作成
教育担当者の負担を軽減し、学習の効率化に直結します。
研究・開発
研究職や技術開発でもNotebookLMは強力なアシスタントになります。
- 複数の論文や特許を比較し、技術要素や相違点を整理
- 学会資料や研究レポートを要約し、素早く知識をインプット
- 技術レビュー会議やブレストの音声ログを解析し、課題や意見を抽出
研究活動のスピードと精度を向上させることで、開発効率の改善に直結します。
カスタマーサポート
顧客対応の現場では、過去の問い合わせデータやマニュアルを活用して即応が可能です。
- 製品マニュアルやFAQを読み込ませ、顧客の質問に瞬時に回答
- エラーメッセージや不具合事例に基づいて、原因と解決策を提示
- サポート担当者同士でノートを共有し、ナレッジベースを強化
顧客満足度を高めながら、サポート工数を削減できます。
副業のChatGPT活用を学ぶなら「AIスキルアカデミー」の講座がおすすめ
生成AIを業務に取り入れる際、「NotebookLMのような資料ベースのAI」と「ChatGPTのような汎用AI」をどの場面でどう使い分けるかが重要になります。
しかし実際には、
- ChatGPTにどんな質問をすればよいのか分からない
- 文章生成やデータ整理の精度を上げたい
- 社内で安心してAIを活用するためのルールを整えたい
といった課題を抱える方も多いはずです。
そんな方におすすめなのが 「AIスキルアカデミー」のChatGPT活用講座 です。
基礎的な使い方から、業務効率化・資料作成・マーケティング活用まで、実務で役立つプロンプト設計や事例を体系的に学べます。
さらに、初心者の方でも安心できるよう、無料体験セミナーも開催中。
NotebookLMとあわせてChatGPTのスキルを身につければ、日常業務の生産性は大きく向上します。
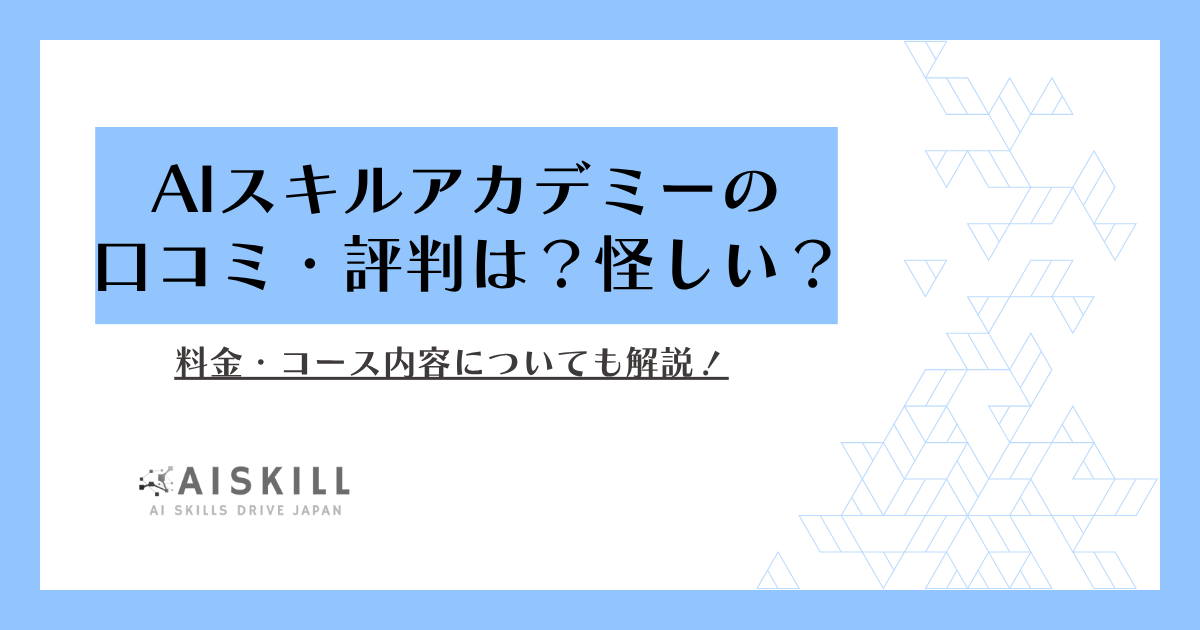
NotebookLMの注意点・リスク

NotebookLMは非常に便利なAIノートブックですが、業務に導入する際にはいくつかの注意点やリスクへの理解も必要です。
以下に代表的なポイントを解説します。
アップロード資料の更新は自動反映されない
NotebookLMにアップロードした資料はコピーとして保存されるため、元ファイルを修正しても自動的に更新されません。
そのため、最新情報を反映させるには手動で再アップロードが必要になります。
特に規程や契約書など頻繁に改訂がある資料を扱う場合は、定期的に更新ルールを決めておくことが重要です。
ソースの質と鮮度が回答精度を左右する
NotebookLMは「与えられた資料の中身だけ」で回答する仕組みです。そのため、資料が古かったり、誤った情報を含んでいたりすると、出力結果も不正確になります。
- 信頼できる資料だけをソースにする
- 古い情報を混在させない
といった運用ルールを守ることで、回答の精度を高められます。
機密情報の扱い
NotebookLMはGoogleのセキュリティ基準に準じて安全に運用されていますが、企業で利用する場合は「どの情報をアップロードするか」の判断が重要です。
- 社外秘の契約書
- 個人情報を含む顧客データ
- 公開前の経営資料
などを取り扱う際は、アクセス権限の管理や「チャットのみ共有」機能を活用することで、情報漏洩リスクを最小限にする必要があります。
無料版の制限とPro版の必要性
無料プランでも基本機能は利用できますが、利用上限があるため本格的な業務利用では不十分なケースがあります。
- アップロードできるソース数
- 1日あたりの質問回数
- 作成できるノートブック数
といった制限により、資料を大量に扱う企業ではPro版やEnterprise版が必須となる場合もあります。
NotebookLMに関するよくある質問(FAQ)

NotebookLMはまだ新しいサービスであるため、利用を検討している方から多くの質問が寄せられています。
ここでは代表的な疑問点に回答していきます。
日本語対応はある?
はい、NotebookLMは日本語に対応しています。
アップロードする資料が日本語でも問題なく要約や質問応答が可能です。
2025年のアップデートでは「音声概要」機能も日本語に対応し、ポッドキャスト風の要約を日本語で聞けるようになりました。
ただし、一部の高度な機能やサポート情報は英語が中心となっているため注意が必要です。
モバイルアプリはある?
2024年5月にモバイルアプリがリリースされ、スマートフォンやタブレットからも利用できるようになりました。
移動中でも資料をアップロードしたり、音声要約を聞いたりできるため、スキマ時間の活用に最適です。
業務用途でも、会議前にスマホで資料を確認するなど活用の幅が広がっています。
ChatGPTとどちらを使うべき?
NotebookLMとChatGPTは得意分野が異なります。
- NotebookLM:アップロードした資料をもとに正確に要約・回答(根拠リンク付き)
- ChatGPT:幅広い知識を活用したアイデア出しや文章生成に強い
業務や目的に応じて使い分けるのがおすすめです。
例えば、「社内規程をもとにFAQを作りたい」ならNotebookLM、「SNS投稿アイデアを出したい」ならChatGPTが適しています。

無料でどこまで使える?
NotebookLMはGoogleアカウントがあれば無料で利用可能です。
ただし無料プランには、アップロードできるソース数や質問回数に制限があります。
本格的に業務で活用する場合は、上限が大幅に拡張された有料プラン(Pro/Plus)を検討するのが良いでしょう。
まとめ

NotebookLMは、Googleが開発した次世代型のAIノートブックであり、従来の生成AIツールとは一線を画す存在です。ユーザーがアップロードした資料を唯一の情報源として活用するため、回答の正確性と信頼性の高さが特徴といえます。
さらに、要約や質問応答に加えて、音声概要やノート保存・共有などの機能を備え、研究・教育・ビジネスなど幅広い分野で活用可能です。特にバックオフィス業務の効率化、営業資料の分析、人事研修の設計、研究開発での論文比較など、具体的なユースケースが豊富に存在します。
ただし、アップロードした資料が自動更新されないことや、無料版の制限、機密情報の取り扱いには注意が必要です。利用する際は常に最新の資料を準備し、業務ルールを整備した上で導入すると安心です。
今後も機能拡張や連携強化が進むことで、NotebookLMは業務や学習に欠かせない存在となっていくでしょう。まずは無料版で試してみて、自分のワークフローにどのように活かせるか体験することをおすすめします。












